 ちごちゃん
ちごちゃん建築めがねさん、1級建築士の資格取得は大変でしたか?



そうだね、、もう思い出したくないくらい大変だったよ。



え?そんなに大変だったの・・
それとも何か嫌なことが?



思い出したくないはさすがに言いすぎたかな。
でも合格するまでに3年以上かかったし、正直合格した年も落ちたと思ったから、もう諦めようと思っていたんだよ。
学校の先生にも多分無理と言われたし・・・



建築めがねさんも苦労しているんだね。



1級建築士の勉強は本当に苦労したよ。センスが本当になかったから、諦めずにやった粘り勝ちだと思っているよ。
これから建築士を目指す人も諦めずに頑張ってほしい。
・1級建築士を目指している方
・1級建築士の勉強をしている方
・諦めずに頑張って1級建築士試験合格を目指す人
(・建築メガネの苦労話を聞いてくれる方)
【3年以上かかったけど合格できた1級建築士】合格まで
私は1級建築士に合格できるまで結局3年以上かかっています。3年以上と言っているのは試験は3回受けており、勉強期間としては4年程度かかっているからです。
ちなみに今は受験資格が変わり受験そのものは実務経験がなくてもできますが、私の時期はまだ実務経験が必要でしたから、実務経験の要件を満たしてからすぐに受験を始めて計3回、3年以上かかりました。
初受験の時の勉強方法について
初めて受験をしたときは、1度で合格できたらラッキーと心の中で思っていたので、本屋で買った過去問を2、3回程度解いて試験に挑みました。
この試験を甘く見ていた私は、結果的に学科試験で落ちてしまいました。
完璧とまではいかないですが、それなりに勉強もしていたので凹みましたが、1級建築士の試験は大変そうだなと感じたのが初回の受験でした。
そして、落ちた時はやはり資格学校に通うぞ!と心に決めたのですが、資格学校の受講料を見て諦めたことを覚えています。正直まだ社会人になりたてで貯金もあったわけではないですし、お金をかけずに合格できれば浮いたお金で色々できるなと思っていたので学校へ通うという選択肢は消えていました。
気合を入れて2年目の受験(学科編)
2年目の受験では昨年の反省を踏まえて勉強方法を変える必要がありました。そんな中、勤めている会社で建築士受験のための研修がタイミング良く始まりました。
研修の内容は、短時間の講義+想定問題を解くというものでした。多くの問題に触れることができたのでとても力になりましたし、これに出ていれば、ひとまずは自分でお金を払って資格学校に通う必要がないなと思い安心したのを思い出します。
自宅では集められるだけ集めた過去問をひたすら解き続けました。
資格試験の学科は建築士に限らずですが、過去問をどれだけ解いたかが合格率に直結していると思います。
学校に通っていない身としては、過去問に頼るしかなかったというのが本音でもありますが、、、
なんにせよ、このタイミングよく始まった会社での研修+過去問の解きまくりにより2年目は学科試験に合格することができました。
自己採点の結果、8割以上の点数が取れていたので合格を確信しました。
(もちろんいくつかラッキー点もありましたが。)
気合を入れて2年目の受験(製図編)
1級建築士の試験が特に大変だと感じたのは学科試験の合格がわかり、製図試験の勉強を始めなければならない時でした。
私は、完全に学科試験で燃え尽きていたので、遊びたい欲、だらけたい欲にとりつかれました。
正直仕事しながらの勉強は大変でしたし、スタミナ切れでした。
製図に関しては会社での研修はなかったので本気で一人で挑まないといけなくなり、受かる気がしなかったことを覚えています。
とは言うものの、私が合格したときは現在と違い好きな年に製図試験を受けられる制度はなかったため、1年見送れば単純に1回分のチャンスを失うことになってしまいます。
なので受けないという選択肢はありませんでした。
やりたくないが、やるしかない。色々な欲求を抑えなんとか製図の勉強をしました。
製図に関しても学科の時と同様に市販で販売されている製図の本を買い、それをもとに勉強を進めていました。
しかし、製図の勉強において最も重要である取り組める課題の数が少ないという問題がありました。
市販の本でも資格学校が出しているものもあり、何問かは想定課題に取り組むことができますが、圧倒的に数が足りませんし、難易度もとても低いものしかありません。
ネットでも製図の講座などがあり、課題を販売(課題文は公開、添削が有料)をしているサイトもありましたが、正直お金を使うことに抵抗が大きかったのでやりませんでした。結局市販の製図本・過去問と資格学校で直前模試が開催されていたのでそこにお金を払って行きました。
ネットで販売されている問題の購入をためらった理由として、公開されている課題を見て、課題の質に懸念があったからです。過去問と比較して、無駄なほど難しく問題文章を長くしていると感じたもの、やたら作図量を増やすための指示が多い問題など。
(製図試験の合格後も思いましたが、本当に無意味な指示が多い課題を公開しているところがあるなと言う感想です。)
基本は市販のテキストだけでしたが、製図練習をこなし、なんとか直前には時間内に製図を終えられるようになっていました。しかしながら自分の描いている製図が果たしてどのような評価なのかが全く判断がつかないので自信は全くありませんでした。
学科の問題集であれば回答は一つなので、自分で答えをみて学ぶことができますが、製図の課題の場合は回答例はあるものの回答は一つではありませんし、何より模範回答通りの図面をかけた事が一度もなかったので、これまた、大丈夫なのかという不安に駆られていました。
ちなみに私は製図のセンスはまるでなかったので、作図時間はどんなに頑張っても3時間を切ることはできませんでした。そのため、エスキスや記述問題を可能な限りつめて、「3時間30分」作図時間を必ず確保するタイムスケジュールで練習をしていました。
製図試験当日、作図が遅い私は、いかにエスキスを早く纏められるかにかかっていたので、いつものタイムスケジュールで時間調整をしながら試験に挑んでいましたが、エスキスが予定時間内に纏まらないという最悪の状態になってしまいました。
しかしなんとか解答しなければということで、エスキスが纏まらぬまま作図に入り、無事にガタガタのプランで回答をしました。時間を守ったので作図は完成まで持って行きましたが、管理部分と利用者動線の交差があったりして散々なものでした。
これ以上時間はかけられない、3年目の受験(製図試験2回目編)
初の製図試験はあっけなく落ちてしまったので、2度目の製図試験に挑むこととなりました。
不合格通知の時点で冬。この時資格学校に通うことは決めていました。
学科と違い独学での突破の道筋が見えないこと、製図の独学はおそらくとても非効率であると昨年の経験から確信したためです。
あとは、独学で合格できたらなんか自信がつきそうだとか、周りに自慢ができるなとか正直思ったこともありましたが、自分は天才ではないですし、独学で合格できたとしても、合格までに時間がかかればそれはお金を払うよりも高くつくと思ったからです。
というわけで資格学校に通うのですが、製図試験2年目の方用の、4月から始まる長期講座ではなく、1年目の人と同じ8月から始まる短期講座に申し込みました。受講料はそこまで変わりませんでしたが、当時は仕事も忙しく正直半年も製図勉強の時間に充てられなかったからです。
ちなみに資格学校に通ったとしてもクラスの半分も合格することはできないという現実があります。
学校に通い真面目に頑張っても合格が確実になるようなものではないため、本当に気合を入れてやる必要がありました。
また、これまでの3年の間、家族には勉強の時間を作るために色々協力してもらっていたこともあり、これ以上は時間をかけられない、家族に迷惑をかけるわけにはいかないというところで、確実にこの年に合格せねばというプレッシャーがありました。
資格学校の勉強は独学の時とは違い、とても効率的だと感じました。
また、先生に自分が描いた図面を、面と向かって添削してもらえることはとても勉強になることがわかりました。
本当に作図図面の添削があるか無いかは成長に大きく影響するなと感じました。
ただ、学校に通い始めて成長できていることは感じていましたが、毎回の課題の評価はあまり良くなく、いつまでも色々な部分を指摘され続けていたのでこのままで合格できるのか、という不安はずっと抱えていました。
(結局課題の最高評価はB程度だったような・・・)
それに加え、やはり作図スピードは上がりませんでした。
そのため、作図時間は変わらず3時間30分確保する時間配分で毎回の課題に取り組んでいました。エスキス時間をつめるのですが、課題の難易度によってエスキス時間は結構変わるので、漠然とですが作図速度を上げられない部分で不安がありました。
しかしながら、学校の先生からは時間内に終えられているならば、作図時間に関しては気にしなくても良いと言われたので、自分の能力に限界を感じ作図時間を短縮することは諦め、「3時間30分」で減点の少ない図面を仕上げることに力を入れるようにしました。
作図時間を無理に短縮させることもできます。
壁面線をシングラインで描くなど、講師の人は色々なテクニックを知っています。
ただ、如何せん自分の図面は綺麗ではなかったので、手を抜いたら本当に図面として見るに耐えないものになると思ったので、時間がかかってもある程度の完成度を出す方法で戦うしかありませんでした。
ただ、作図スピード以外は学校に通うことで手に入れることができたと思います。
試験当日は、エスキスが上手くまとまったこともあり、想定時間配分通りに進めることができ、図面を完成させることができました。
製図試験終了と同時に不合格を確信
時間内に作図も終わり、残りの時間もしっかりと見直しをして試験終了。
ペンを置き、回答用紙の回収が始まったその時・・・
普段は絶対にしない数々のミスを見つけてしまったのです。
製図試験を受けられた方等はご存知だと思いますが、製図試験において法的な部分のミス(書き漏れ、間違い)は一発アウトとなります。
特に近年この法律のミスは厳しくなっており、一つでもミスがあれば不合格となると言われています。
私はこの法律部分に関するミスをしていたのです。
具体的には2方向避難について図面に記入漏れ、延焼ラインの描き忘れです。
また、作図中にプランを少し変更したせいで、管理側から利用者側のエリアに出る動線が無くなっていた。(これは家に帰り変更後のエスキスを見て気づいたことなので、回答図面がどうであったか覚えていないのですが、高確率でそうなっていたと思われます。)
資格学校に通っていると、試験後に自分のプランを復元し、学校で講師の方に評価してもらう時間があります。
この時、評価を受けるまでもなく不合格だと思っていたので、自分のプランを復元したくもないと思っていましたが、手ぶらで行くわけにもいかず、フリーハンドでやる気のない復元図を持って学校に行ったのを覚えています。
評価を受ける前に、自分がやってしまったミスを一通り先生に話をしました。
プランは悪くなく、まとまっているとの評価でしたが、自分で思っていた通り、法律部分のミスがあるので、不合格でしょうという評価でした。(不合格とはっきり言われたわけではないですが、厳しいですと言う回答でした。)
その後、別部屋で営業の方に次年度の申し込みを進められる始末。
しかしながら、もうこれ以上家族に迷惑をかけられないので、次年度の受験は考えていませんでした。
不合格なら子どもが手を離れたあとにまた受けようと決めていたのです。



一発不合格があるってなんだか理不尽な試験だね。



そうだね。受験する側からするととんでもない。という気持ち。
でも1級建築士として仕事をすることはそれだけ責任が重いということなんだよ。特に建築基準法を満たせていない建物を設計してしまったら人命に関わることになるしね。



そう言われると・・・
法律を守れない人が合格になるのはまずいね。。
家とかって安心できる場所ということが重要だし。



家は安心できる場所でないといけない。
だからこそ法律を知らない建築士が合格しないように試験を厳しくしているということだね。
学校から合格の連絡
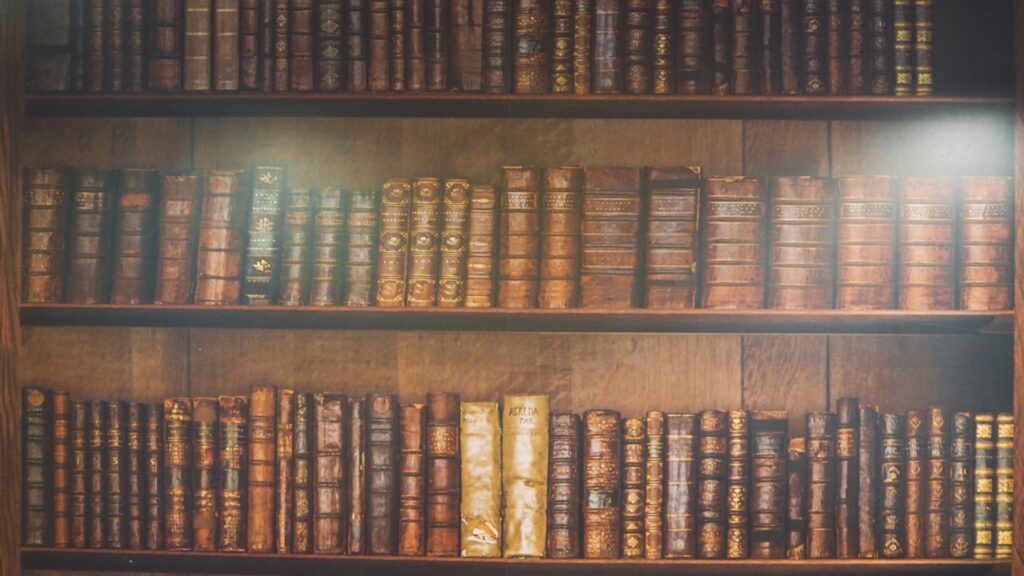
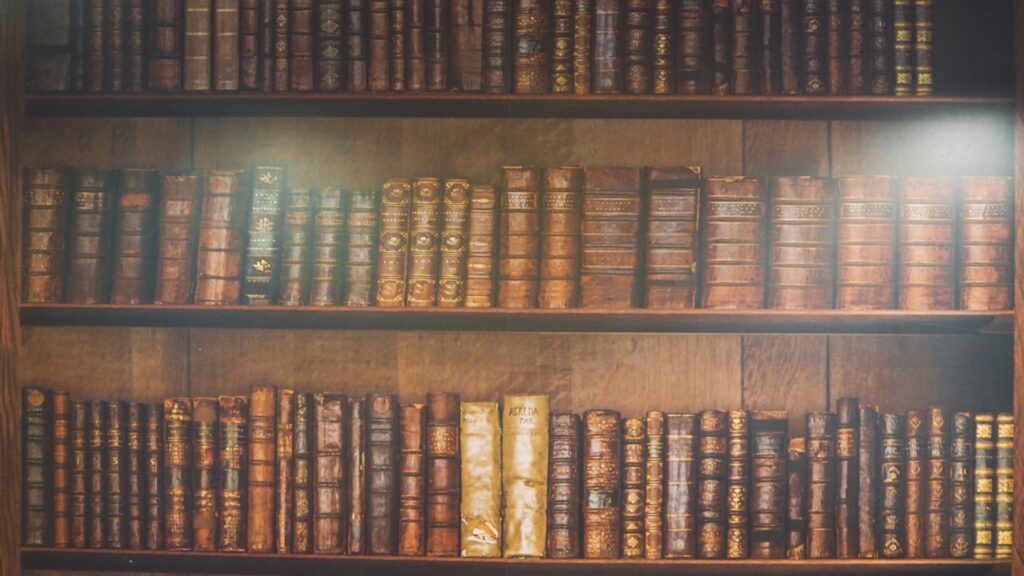
合格発表当日、自分は不合格を確信していたので、合格発表のことはできるだけ忘れるようにしていました。
営業の方から電話がかかってきた時も、不合格の連絡だなと思いながら嫌々電話に出たことを思い出します。
製図試験の勉強は本当に大変だったので、電話をとった道端で嬉し泣きをしました。
すぐに家族にも連絡しました。
というわけで、色々と大変でしたが1級建築士に無事合格をすることができました。
製図試験については、今考えても合格の基準が良くわからない試験だとはっきり思います。
ただ、大きなミスを(恐らく)しながらも合格できたことで、なんとなくの合格図面について考察ができたので、別記事でまとめています。
1級建築士の資格をとって良かったか?
1級建築士の資格は、会社から必ず取れと言われていたわけではなく、仕事のためというよりは、私自身の小さい頃からの夢だったという理由が大きいです。
私の場合は1級建築士を取って良かったかと聞かれれば、自分の夢だったのでもちもんよかったと答えます。
一方で、仕事面で考えても、間違いなく取ってよかったと言う回答になります。
1級建築士の資格を持っていなくとも、建築の知識が多く信頼されている方がいるのも確かです。逆に1級建築士の資格を持っていても経験の少なさから、あまり詳しくない方が多いのも確かです。
(私自身もまだまだ切磋琢磨しております)
ただ、社外の方の信頼を得る方法として、資格を示すことほど単純かつ近道な方法はないです。
社内の方に対してであれば資格なんてなくとも良いです。社内の人へは知識や経験を毎日の仕事の中ではっきり示すことができるし、本当に能力があれば社内の人が評価してくれるからです。
社外の人に対してももちろんそういった知識や経験を感じさせることはできますが、時間がかかります。また、逆の立場にたつと、知識は豊富だが資格がないからすぐに言っていることを信用はできないと少なからず感じると思います。
資格を持っている人の方が偉いとは決して思いません。
ただ、資格を持っているということは、これまで真面目に取り組んでいたことを証明する、唯一の方法なのだと思います。
建築に関しての知識などを話す際の説得力が資格が有ると無いでは大きく違います。
色々なことを記載しましたが、1級建築士の資格が業務で必須でない人であっても、資格をとる価値は十分にあります。



建築めがねさんは1級建築士になるのが夢だったんだね。



そうなんだよ!
とはいっても昔に思い描いていたセンス抜群の意匠設計ができる建築士にはなれていないけどね・・・
まとめ
この記事では、建築めがねが1級建築士に合格するまでについて記載をしました。
どなたかの参考になれば嬉しいですし、なかなか合格ができない人も諦めずに頑張ってほしいと思います。
ところで1級建築士に合格するまでの道のりをこの記事にまとめながら改めて振り返ってみての反省点は、時間をかけすぎたな・・・というところです。
もっと早く合格していれば色々他のことができたなと正直思います。
まぁ当時の自分にはお金もなかったし仕方ないのですが、最近は質の高い通信講座もあるので、そういったもので学科試験の一発合格を目指す方がいいと感じます。
今後も、1級建築士の勉強についてや製図試験で役に立った道具などを紹介していけたらと思います。
これから1級建築士を目指される方にとって有益な情報を記載できたらと思いますので、よろしくお願いいたします!!


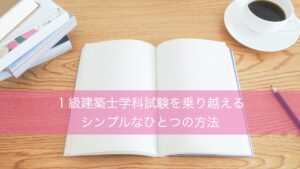

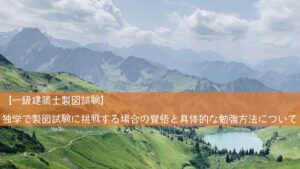


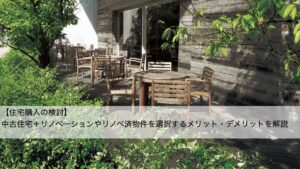

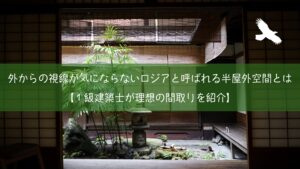
コメント