 ちごちゃん
ちごちゃん建築めがねさん、1級建築士の製図試験って合格基準がよくわからないとか、一発不合格があるとか聞くけど実際どうなの?



その通り・・・
合格基準は不明確だし、一発不合格もある試験だと思うよ。
私自身も落ちたと思った試験で、学校の先生にも難しいと言われたけど結果的に合格できて、やはり合格基準は謎だなーって感じたよ。



やっぱりそうなんだ!
基準がよくわからない試験って攻略が難しそうだね・・・



そうだね。
ただこれだけは絶対にやってはいけないポイントがあるから、ここだけは抑えたいというポイントを今回の記事ではまとめようと思うよ!
・1級建築士製図試験でおさえておきたいポイント4つ
・記入漏れ、間違いで一発アウトとなる項目は?
・まとめ
1級建築士製図試験でおさえておきたいポイント4つ
製図試験については、ネットで検索をすれば、どういったポイントが重要視されているか分かりますし、資格学校では減点項目を明確にして、どういった点に注意をするかということを教えてもらえます。
色々な所から様々な情報を集めることができますが、この記事では実際に私が受験・合格をして実感したことについて、おさえておきたいポイントについてまとめました。
ゾーニング:管理エリアと利用者エリアの動線、ゾーニングは必ず明確に分ける!
建物の計画をする上でゾーニングは重要な要素となります。そして、まず、第一にゾーニングがしっかりとできていないとほぼ合格にならないと考えられます。
事実私も初年度の図面ではゾーニング・動線が不明瞭なところがありましてランク3でした。(もちろんそれだけではないですが)
資格学校等でもよく言われていることですが、プランを描き上げた後に、気付かないところで動線が交差してしまっていたり、管理エリアの範囲が不明確となっているプランはよくあります。
私が学校に通っていた時も、自分や資格学校での他人のプランを見ても本当によくありました。
動線の交差を避けることやゾーニングの明確化はプランを組み立てる上で最も基本的な部分であり、採点側からすれば最も簡単にわかる部分であるので、減点をし易い部分であると言えます。
採点側の立場で考えてみると、膨大な図面を確認しなければならないわけですから、簡単に合格・不合格を分ける項目をもっているはずです。その一つがこのゾーニング部分であると思います。
これまでの試験問題の回答例をみてもゾーニングは明確なものが多いです。(一部これもありなのと思うものもありますが・・・)
過去問題:https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-mondai.html
余談ではありますが、資格学校でタブーとされていることが意外と試験元の標準回答例で使われていたりするので、学校で言われていることを全て鵜呑みにして、試験当日エスキスがまとまらないくらいならば、タブーをおかしてでも図面をまとめあげたほうが良い場合があります。(もちろん法律部分を無視するのはダメですが)



管理エリアと利用者エリアを分けるのは分かったけど、具体的にどうやって区分けするの?



管理エリアと利用者エリアを明確に分けていることを示すには、管理側と利用者側の境界にドアを設置することが必要!
ドアをつけて、管理者しか入室できないようなセキュリティ(カード認証)を設けることが簡単な方法だよ!(会社とかでも多いよね。)



そうか、考えてみると、お店とかでも関係者以外はこの先立入禁止とかよくあるよね。あそこが利用者と管理者エリアの境界か。



そうそう。
例えば、管理側は、高齢者介護施設であれば介護者の方がいるエリア、事務所ビルであればビルの管理人や警備員の方がいるエリア。
基本的にその建物に訪れた人が、自由に入れるとよくない部分が管理側で、セキュリティに配慮しないといけないよね。
建物配置:メイン動線となるエントランスの位置に注意
建物配置はプランを練る上で重要な要素となります。そして、敷地が面している道路幅によってメインエントランスの位置を決めますが、メイン動線となるエントランスの位置はプランの完成度に大きく影響するため重要なポイントと言えます。
基本的には広い道路に面している部分をメインエントランス、次に広い道路に面している部分を管理側の通用口として設けることが鉄則です。そして、エントランスまでに至る敷地内の通路を明確にすることや訪れた人が迷わず向かえる位置となっていることも重要です。
一面しか接道していない敷地の場合は、入り口配置が難しい場合がありますが、メインエントランスを敷地の中央付近に配置し、管理動線は端の方に設けることが基本的な配置になります。
あとは、外構部分に色々指定があるとエントランスを含めた建物配置はとてもむずかしくなります。例えば、曲者といえるのが車回しなどです。駐車場、駐輪場もですが、外構部分に縛りが多いと配置計画がむずかしくなります。
配置計画をする上で、問題の条件が多い場合、問題文を読むことに加えそれぞれの関係性(駐車場の位置や建物配置、そしてメイン動線となるエントランス位置等)を把握することに時間がかかってしまいます。
ただ、縛りが多いと言うことは合格となる回答図面のレパートリーとしては少なくなるので、時間がかかっても整理さえできれば減点の少ない図面を描ける可能性もあがります。
実際に課題に慣れてくると、条件の整理はスムーズにできるようになるので、条件が多い問題の方がプランが早く決まることが私の場合は多かったです。
一方で問題の条件が少ない場合、計画上はどこにでもエントランスを設けられ問題が易しいと感じます。
しかしながら、条件が少ないからと言っても、出題者が考えている配置計画の大前提はあるわけで、問題文の中で暗に示されている周囲との関係性などの配置条件を見落としてしまうと、大減点となります。
明確な指定条件が少なく楽だと感じる問題ほど、キーとなる条件を見分けるのがとても難しく、プランを確定するのに時間がかかります。
というわけで、建物の配置計画を考えるときは周囲との関わりを踏まえて、
「どこから人が訪れるのか?」
「エントランスは1箇所だけで良いのか?」
などを考えながら決める必要があります。
平面計画:”無”となる空間を作ってはいけない
プランを作る際に課題の種類によって、必要居室を入れ込むとカツカツとなる問題と指定されている居室を入れただけではスカスカとなる問題があります。
この2つの内、指定された居室だけでプランがカツカツとなる問題の場合はあまり気にしなくてもよいのですが、内部空間に余裕がある問題の場合は注意が必要です。
基本的に、製図課題に取り組むときは、敷地に可能な限り大きな建物を計画することが鉄則となります。
その最大サイズの建物で内部のプランを成立させていきます。この時、指定された居室が少ない場合や居室の必要面積が小さい場合、内部に無意味な空間、デッドスペースが生まれる場合が多いです。こうした何も計画されない空間がある場合、建物が無駄に大きくコストがかかると判断され減点されてしまいます。
それでも問題の性質上、余裕のあるプランとなる場合は、無の空間がまったくないプランを計画することはとても難しいです。
そのため、”無”とならないように配慮することが大事です。
例えば、微妙に余ってしまう空間については、トイレ、休憩エリア、展示エリア、倉庫、コインロッカーなど特に課題上は要求されていないが、建物にあっても不思議では無いものとすることで対処できます。
あまりにトイレが多い、倉庫が多い場合などはよくないので、無の空間を何らかの意味のある空間とするレパートリーを、普段の課題や過去問を解いていく中で身につけていくことが大事だと思います。
すこし危険な点として、こうしたスペースを設けたことで2方向避難等の法的な避難距離が満たせなくなってしまう可能性があります。こうした場合は法律優先で無理に部屋などを作らないようにしましょう。
断面計画:問題の条件、設備計画を考慮した階高・天井高を確保
天井高は、利用者エリアについては基本的に3m程度を確保したいところです。
一方で、管理エリアや便所などは2.5m程度でいいですが、利用者エリアの天井高を確保するために、階高としては4mを見ておくことが望ましいです。
例えば、単一ダクト方式などでダクトが天井内に入る場合は階高4m確保しないと天井高3mの確保が難しくなります。(大雑把に大梁+ダクトの必要高さを考えると1m程度必要なので、階高4mで天井高3mとなります)
設備計画でダクトを使っているのに階高が足りていない図面になっていると計画が成り立っていないということで、大減点されてしまいます。
一方で、マルチ型エアコンなどであれば冷媒等を運ぶ配管さえ天井を通ればいいので、階高としては3.5mで十分となります。
無駄に階高を高くすることはコスト面でマイナスですし、最悪高さ制限などに引っかかる場合があるので適切な高さで計画する必要があります。
ところで、断面図を書く際、利用者エリアを天井高3mで計画したからと、管理側や便所などの天井高さも同一の3mとして作図されている方はいませんか?
作図としては楽なのですべて同じ天井高で計画したいところですが、ここはしっかりと、管理側廊下2.8m、便所2.5mなど天井高を分けて作図をすることで現実的なプランとなりますので、ここは楽をせずに書いた方が印象が良い図面になると思われます。
余談ですが、天井高を確保するために無理に階高を上げすぎると、道路斜線制限などに引っかかる場合もあるので注意が必要です。特に全面道路の幅員が狭い時や敷地が狭い時などは注意が必要です。高さが出ても道路側からセットバックすればいいのですが、敷地が狭いと逃げ場がなくなってしまいます。
記入漏れ、間違いで一発アウトとなる項目は?


一発アウトになる項目については諸説ありますが、明確なものは法律の部分に関するミスです。
特に、近年は法律部分の確認が細かくなっており、その影響により、ランク4による不合格図面が、過去よりも明らかに増えています。
採点者側からすれば採点が楽になりますし、不合格の判断も明確なのでいいですよね。
法律的な部分でアウトとして挙げられる項目は多くあると思いますが、書き漏れや間違いで1発アウトで思いつくものを下記に列挙します。
一発アウトとなる可能性が高い項目
・建蔽率、容積率、階数、構造・設備方式など建物計画の根幹となる部分の間違い
→このあたりは計画する上で必ず守らなければならない部分のため、ここを間違える(勘違いする)と一発不合格の可能性が高いと考えられます。
・道路後退による敷地計算間違い
→4m未満の道路がある場合は、道路後退を考慮して敷地面積を計算する必要があります。
・床面積の計算ミスで指定面積を満たしていない場合
→PSやEV部分を含めるのかなどは問題により微妙に異なるのでしっかりと確認する必要があります。
・建物高さが道路斜線制限等の最高高さを超えてしまったもの
→目の前の道路が6m以下、建物が2mしか後退できていない場合などは少し危険です。
・防火設備、特定防火設備の記入漏れ、適切でない場所に設けているもの
→面積区画、竪穴区画、異種用途区画なのかを意識して適切に計画する必要があります。悩む部分は特定防火設備として逃げるのも手かもしれません。
・延焼ラインの距離間違い、延焼ラインかかる部分の防火設備記入漏れ
→延焼ラインは1階3m、2階5mですが、1階に延焼ラインが出てこないからと2、3階へ記載するのを忘れてしまうケースがあるので注意です。(実体験です)
・PS、DS、EPS、空調用PS、アラーム弁室の記入漏れ
→このあたりは計画忘れが多いです、特に空調用PS。また、DSのサイズは空調計画により変わるので注意が必要です。
・2方向避難の距離が守れていない
→法律部分なのでまずいミスです。描き上げてから階段の位置を変更することなどは困難なので、エスキス時点でしっかりチェックしておきます。いざというときは屋外階段を設けることで回避できますが、本番で慌てて屋外階段を計画するとどこかでミスをするので、練習をしておくとよいです。
・屋外階段から道路までの避難通路がない
→屋外階段を計画した際は、そこから道路まで出る敷地内避難通路を計画する必要があります。
これら以外にも重要な居室の面積や天井高さ等の条件が満たせていない場合は大きな減点となります。
また、施設の中で重要となる空間(例えば美術館であれば展示室など)は細かい条件が指定されている場合が多いので注意が必要です。
よって、例えば、管理エリアの居室を広くとりすぎてメイン空間の面積条件を満たせていないようなプランは避けるべきだと言えるのではないでしょうか。
製図の問題はプランを組み立てていくとどうしてもすべての条件を満たしきれない場合がでてきます。その時に切り捨てるべきは管理側の居室、倉庫、便所、利用者側の重要でない小さな居室等の面積を削ることです。メインとなる空間の面積を削ることはしてはなりません。
プランを計画するときは最も大きい空間から平面プランにはめ込んでいくことが重要です。



こんなに一発アウトの項目あるの。覚えられないよ。



100%これらの項目で一発アウトとなるかは分からないけど、
でも自分がやっていた時は学校からこれくらい言われたよ。
この項目を言葉として暗記するというよりは、作図が終わった後の習慣として本番までに身につけるイメージだね!
まとめ
設計製図は答えが1つではない、採点基準も不明確であるというところで、勉強方法が難しいと言えます。
一発アウトと判定される、言わば罠的な部分も多くあり、しっかりと完成させた図面でも気づかないところでアウトの判定をされてしまう場合があります。
一発不合格の項目は採点者でないともちろん分かりませんから、可能な限りこの項目を理解すること。
そして、徹底的に見直しをしてミスのない図面を目指す必要があります。
こうした危険項目を頭に入れ、作図途中や終了後に確認をする習慣を身につけられるまで練習あるのみです。


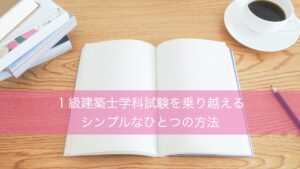

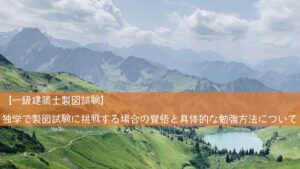


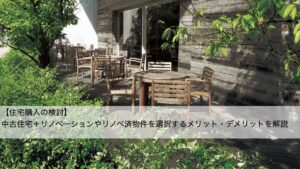

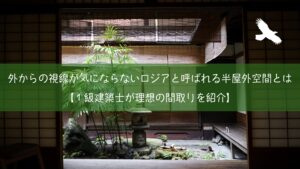
コメント